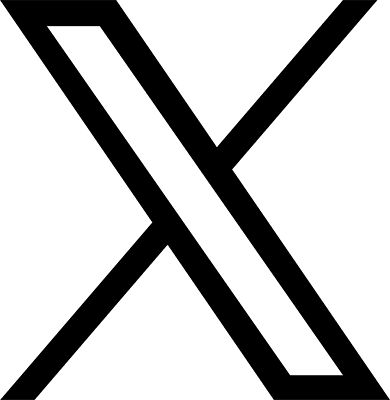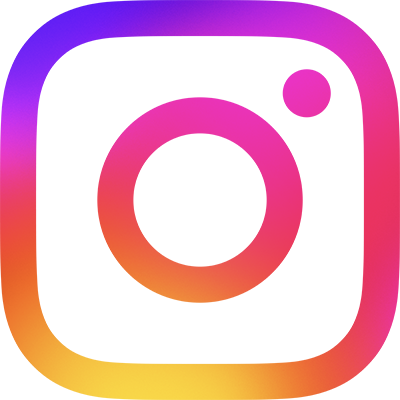血液内科・貧血外来
当院血液内科の特徴
- がん診療拠点病院勤務の血液内科専門医が予約なしで対応
- 基本的検査項目は当日30分以内に結果が判明
- 近隣の婦人科や消化器内科とも連携、適切な大学病院や総合病院に紹介可能
息切れやふらつきなど、ありふれた症状にも血液の病気は隠れています。軽い貧血や白血球が増えているなど検診で見つかっていても、大きな病院の受診をためらわれている方もいらっしゃいます。そうした方もお気軽にご相談ください。また、院長は抗がん剤や放射線治療を受けられた患者さんの長期的な合併症管理の専門外来をがん診療拠点病院で行っております。がん治療を受けられている方や治療後の方の慢性疾患の管理も対応させていただきます。既に他の医療機関で血液疾患と診断されている方の外来通院も病気によっては対応可能ですが、その際には主治医を通じて事前にご相談をお願い致します。
鉄欠乏性貧血について
鉄欠乏性貧血はこんな病気

鉄欠乏性貧血は鉄分が不足することで酸素を運ぶヘモグロビンが作れなくなる貧血です。2009年の調査では20~40代の女性の約40%が鉄欠乏状態にあったとされています。日本では先進国の中でも貧血の患者さんの割合が多いにも関わら ず、 85%以上が無治療とされ、 年間で3兆円を超える過剰な医療費と1兆円を超える生産性の喪失を起こしていると推測されています。
鉄欠乏性貧血の症状・診断
以下のような特徴があげられます。
- 疲れやすい、ふらつきを感じる
- 階段や坂をのぼると息切れする、動悸がする
- 顔色が悪いといわれる
- 爪が割れやすい、へこんでいる
- 氷をよく食べている
- 飲み込みにくさを感じる
- 肉をあまり食べないなど偏りがちである
これらの項目のうち3つ以上当てはまる、あるいは2つであっても症状が強いなどの場合、
起立性調節障害を疑います。
ほかの病気ではないことを確認した後、新起立試験(10分間安静の状態で横になった後に起立し、心拍数や血圧の変化を測定)を行ない、以下の4つのどのタイプに当てはまるかを判定します。
血液検査を行い貧血の値と体の鉄分を確認し、診断を確定します。生理中、鉄剤やサプリメント内服中などは貧血や鉄分の値だけでなく、赤血球の大きさや若い赤血球の割合の変化も参考にします。当日結果が判明するような基本的な検査項目だけでも、鉄欠乏以外の原因についてある程度は判断可能です。また、女性の鉄欠乏は生理の時の出血が一番多い原因ですが、他の出血を起こす病気や鉄分の吸収を妨げる病気が隠れていないかも注意します。
貧血が進行して息切れや動機を感じなくても、慢性的な倦怠感や疲れやすさの原因となっていることがあります。コラーゲンを作る際にも鉄分が必要であり、爪の変形や脱毛、咽頭違和感を起こすことがあります。また、妊娠に際しては、早産や低出生体重児の増加との関係が指摘されています。
慢性的な貧血状態では体が慣れており、負荷がかかっていても息切れなどの症状に気づきにくいことがあります。検診で貧血が指摘された時などは、生活に支障が出る前でも鉄分の状態について確認しておくことが重要です。
鉄欠乏性貧血の治療
食事からの鉄分摂取が基本となりますが、令和元年の調査によると1日鉄分摂取量は成人男性で8.0mg、成人女性で7.3mgであり、成人女性の推奨摂取量10.5mgから40㎎を大きく下回っています。食品に含まれている鉄には肉、魚、卵などの動物性食品に含まれるヘム鉄と野菜や海藻、大豆などの植物性食品に含まれる非ヘム鉄に分かれます。吸収率はヘム鉄が50%、非ヘム鉄が15%と考えられており、日本人では植物性食品による非ヘム鉄の摂取が中心です。非ヘム鉄はビタミンCの摂取によりヘム鉄となり鉄分の吸収効率が増します。したがって、肉や魚にくわえて野菜、果物をバランスよく食べることが重要です。ただし、女性の鉄欠乏性貧血は食事による摂取不足よりも月経による鉄喪失の方が影響は大きいと考えられており、過剰な鉄分摂取は勧められません。バランスの良い食事を摂取しても貧血が改善しなければ薬物療法を行います。
現在、内服薬は5種類、注射製剤は3種類が使用可能です。長く使われてきたクエン酸第一鉄ナトリウム(フェロミア® )などの経口鉄剤は消化器症状の合併が低頻度ながら問題になることがありました。睡眠前に内服する、徐放錠を使用する、再少量から増量していくことで治療の継続が容易になることがあります。また、最近一日おきの投与でも毎日内服する場合と遜色ない効果が得られることが報告されました。こうした方法でも投与継続が難しい場合はこれまでは注射製剤を使用されてきました。最近使用できるようになったクエン酸第二鉄水和物(リオナ®)は90%以上の患者さんで内服治療を継続できたと報告されており、これまで点滴治療が必要な方でも内服治療で対応できることが多くなりました。内服治療でも十分な効果が得られない場合、内服治療が困難な場合は、注射製剤を使用します。以前は連日の注射が必要でしたが、最近使用できるようになった新規薬剤(フェインジェクト®、モノヴァー®)により2-3回の投与で十分な貯蔵鉄の補充が達成できるようになりました。こうした薬剤により患者さんの受診回数も少なくて済むようになってきました。内服治療と同時に症状や治療経過に応じて、婦人科疾患や消化管疾患の合併についても評価や治療も検討します。
貯蔵鉄を反映するフェリチンが20-30ng/dL以上となると一旦治療の中止も検討されます。症状が持続する場合や貧血に容易に陥る場合は、鉄剤の内服を土日だけ、生理の出血のときだけ、など減量して継続する方法もあります。
まとめ
血液検査を行い貧血の値と体の鉄分を確認し、診断を確定します。生理中、鉄剤やサプリメント内服中などは貧血や鉄分の値だけでなく、赤血球の大きさや若い赤血球の割合の変化も参考にします。診断時には鉄欠乏以外の貧血の病気を合併していることもあるため、特に治療の反応性が悪い際には注意します。また、女性の鉄欠乏は生理の時の出血が一番多い原因ですが、他の出血を起こす病気や鉄分の吸収を妨げる病気が隠れていないかも注意します。
貧血が進行して息切れや動機を感じなくても、慢性的な倦怠感や疲れやすさの原因となっていることがあります。コラーゲンを作る際にも鉄分が必要であり、爪の変形や脱毛、咽頭違和感を起こすことがあります。また、妊娠に際しては、早産や低出生体重児の増加との関係が指摘されています。
慢性的な貧血状態では体が慣れており、負荷がかかっていても息切れなどの症状に気づきにくいことがあります。検診で貧血が指摘された時などは、生活に支障が出る前でも鉄分の状態について確認しておくことが重要です。
※参考文献
令和元年国民健康・栄養調査報告
J Med Econ. 2023; 26:1386-1397.
Turk Pediatr Ars. 2015; 50: 11-19.
Ann Hematol. 2023; 102: 145–152.
臨床血液2021; 61: 1583-1592.
Int J hematol. 2019; 109: 41-49.
Int J hematol. 2022; 116: 846-855.
多血症について
多血症は血液中の赤血球が増加している状態です。頭痛やめまいなどの症状を認めることもありますが、健康診断で血液が濃いと指摘される無症状の方も多くいらっしゃいます。遺伝子異常による一次性の多血症 (骨髄増殖性腫瘍)と喫煙や睡眠時無呼吸症候群が原因となる二次性の多血症とがあります。特に前者は脳梗塞など血栓症との関連も指摘されており、早期に正確な診断とリスクに応じた治療を行う必要があります。また、後者では合併する生活習慣病や睡眠時無呼吸症候群の管理が重要になります。
当院では診断に必要な遺伝子変異解析などの専門的検査や耳鼻科と共同で睡眠時無呼吸症候群の評価・治療も行えます。症状がある方はもちろん健康診断で異常を指摘された方もお気軽に受診ください。
※参考文献
Curr Hematol Malig Rep. 2022 Oct;17(5):155-169.
M蛋白について
検診などでM蛋白の疑いを指摘されることがあります。本来抗体を作る血液の細胞である形質細胞に異常が生じることで、異常な役立たずの抗体が作られます。この抗体をM蛋白といいます。
形質細胞ががん化する多発性骨髄腫という病気ではM蛋白が蓄積され、貧血や腎障害、骨折などの症状が出現します。M蛋白は多発性骨髄腫の前段階や原発性マクログロブリン血症などの類縁疾患、悪性リンパ腫などでも認められ、腎障害やしびれの原因となることがあります。一方で、M蛋白を認めても10年以上治療を要さず、定期的な血液検査による経過観察で十分なこともあります。このように非常に幅広い疾患群を含んでいるため、無症状であっても一度専門外来の受診が必要です。
こんな症状が見られたらご受診ください
- 健診で血液の異常値を指摘された
- 息切れしやすくなった
- ちょっとした出血でもなかなか血が止まらない
- 覚えのないあざや内出血ができやすい
- 氷を食べてしまう